Secret Novel
Secret
Novel
シークレット小説
紅いドライフラワー
失ってから、初めて気づくものだってある。自分の周りにいて当然だと思っている内は、たいして興味もなかったのに。ずっと私を照らしてくれる、太陽だと思っていたのに。存在しなければ生命活動が停止してしまう。あんなにも、唐突に、脆く、消え去るんだ。骨の髄まで私を焦がそうとしていたのに。熱くて、熱くて、嫌だったのに、見放された私の心は、冷たく暗い砂漠を苦しみながら彷徨った。おそらく、死ぬまできみのことは忘れられないだろう。こんなにも私の心に形作っているのだから。
◆◆
雨の中、彼の墓に、花束を手向ける。供えてあった枯れた花が雨風でばらばらに散り、私の足にぶつかりながら、地面を転がる。

アイザック・ドゥ・フィード。
彼のことは、学生時代から知っている。武術面で成績が優秀な男だ。貼り出されているのを見たから分かる。学術的には下から数えた方が早かった。そのおかげで、上の方にいた私は彼に嫌という程頼まれて、勉強を教える羽目になった。彼に付きまとわれるのが鬱陶しくて、渋々了承したのだ。お礼に、武術の訓練に付き合ってやる、と半ば強引に提案された。
「レイ、次はどう解くんだ?」
「はぁ…気軽に呼ばないでもらえるかな」
燃える太陽みたいな色の短髪をかきあげながら、私の名前を馴れ馴れしく呼ぶ姿に、うんざりした。何回注意しても暑苦しいコミュニケーションには、慣れるしかないのだろうか。こういう、繊細とは程遠い奴は正直苦手だ。
「いいじゃねえか。堅苦しいのは嫌いなんだよ。オレのこともザックでいい」
頭の後ろで手を組みながら、椅子の後ろ足だけでゆらゆらとバランスをとっている。落ち着かない。自分たち以外誰もいない教室に、椅子が軋む音が響く。
「これは、ここの公式とここの公式の二つに代入して解く」
説明しながら、全然使い込まれていない綺麗な彼の教科書に、付箋を貼る。
「これか。よし、やってみる」
そう言うと、私に眩しい笑みを向けた。私と彼の間にある机に、夏の光が静かに差し込む。この光のように、何もかも焼き尽くしてしまいそうな真っ直ぐな彼の眼差しは、好きだ。
◆◆
卒業して、私は王立騎士軍参謀部に、彼は王立騎士軍 1 番隊に所属することになった。特に大きな戦争がない平和な時でも、国内の問題は山積みで私は忙しく歩き回っていた。彼は、力の抜き方が上手いのだろう。たまに私のもとを訪れてはささやかな会話を届けてくれた。
「なあ。無理すんなよ」
業務の間の短い休憩時間を中庭で過ごしていると、彼に声をかけられる。様子を見にきてくれたんだろう。声だけで誰か分かった。振り向かずに、古びたベンチに座りながら眠気覚ましのコーヒーを飲む。
「1 番隊は、よっぽど暇を持て余しているんだな」空を見上げる。鳥が輪を描いて、飛んで行った。
「ははっ、相変わらず今日も冷てえなぁ。オレも休憩に来たんだよ」カラッと晴れた夏の青空のように豪快に笑うと、私の隣に腰掛ける。
「疲れてるだろ?今度の休日、オマエん家に行って旨いもん作ってやるよ」
「は…?」
今までプライベートを一緒に過ごすことはなかったため、突然の申し出に驚いてしまった。
「安心しろよ。料理の腕には自信があるんだぜ」
「あぁ…」
「楽しみにしとけよ!じゃ」
睡眠不足で頭が回らなかったのか、判断が遅く、断り損ねた。さっきまで隣に座っていたかと思いきや、ひらひらと手を振りながら、私を中庭に残し大股で去って行った。台風のような男だ。
◆◆
部屋の中を、そわそわと、歩き回る。本当に、来るのだろうか。せっかくの休日が、乱れた心で台無しになる。何か飲んで落ち着こうと思い、コーヒーメーカーのスイッチを入れる。来なかったら来なかったで、いい。暑苦しい奴に私の安らぎを邪魔されたくない。できあがったコーヒーをマグカップに注ぎ入れて、口をつける。
「熱っ…」
疲れているのだろうか。いつもなら火傷なんてしないのに。呼び鈴の音が聞こえ、心臓が一瞬だけ、止まった。
施錠を外してドアを開けると、たくさんの食材を持ったアイザックが待っていた。
「よう。レイちゃん!」
「…」
さらに馴れ馴れしくなっていることに嫌悪感を抱き、そっとドアを閉じようとする。
「あ〜冗談だって!邪魔するぜ」
ドアを軽々と肩で押しのけ、のし、のし、と重い一歩がキッチンまで続いていった。
「私も手伝うよ」
キッチンを滅茶苦茶に汚されたら堪らない。監視の意味だ。
「お前はいい、疲れてんだろ。オレに任せて休んでてくれよ」
食材と調理器具をカウンターに置く音が聞こえる。準備をしているようだ。
「でも…」
来客に無理はさせたくない。と言う前に、物凄い力で体を押され、ソファに座らされる。
「良い子で待っててくれ。な?」
まるで子供に語りかけるような口調だ。私を何だと思っているのか。
「はぁ…分かったよ」
彼は、満足そうな顔で頷くと、再びカウンターに戻り作業をし始めた。その姿を見届けると、買ってからずっと読めていなかった本を一冊手に取る。ソファでくつろぎながら、ページを捲る。仕事以外のことに時間を費やすのは、いつぶりだろう。最近はずっと寝て過ごしてばかりだった。彼に借りを作ってしまった…。
美味しい匂いがして、意識が戻る。本を読む内に、いつの間にか寝てしまっていたようだ。手から滑り落ちて、床に広がっている本を拾う。
「おはよう。もうすぐできるから」
「ああ…」
見られていたのか。気まずさで頭を搔く。だが、まだ料理ができていないところを見るに、そんなに時間は経っていないようで、安心した。本に栞を挟んで、本のタワーの上に積み重ねる。
「ほら、できたぞ」
ドンッとどんぶりがテーブルに置かれ、肉の香ばしい匂いが漂う。量が、多い。どんぶりに白米が敷き詰められ、その上に大量の肉──おそらく牛肉が積まれ、一番上に卵黄が飾ってある。野菜は…散らされたネギくらいだ。こんなに栄養バランスが崩れているものは、あまり食べたことがない。
「どうした?食べないのか?」
彼は、向かいに座り、私のより大きいどんぶりで同じものを食べている。口元に米粒をつけ、頬張りながら、私に話しかけている。
「何でもない。いただきます」
箸で卵黄を割り、米と肉を均等に掬って口に入れる。素直で、シンプルな味だ。
「旨いか?スタミナがつくぜ」
「ああ。美味しい…きみって、料理できるんだね」
「弟に、作ってやんなきゃいけねえからな」
弟がいるんだ。無駄に面倒見が良いから不思議に思っていた。
「あぁ、そうだ。あと酒買ってきたんだ。これ飲んで全部忘れちまえよ」
口をもぐもぐさせながら、袋から酒を取り出す。ウィスキーだ。生まれてこの方、嗜んだことはない。彼は、瓶の蓋をひねって開けると、氷をギッシリ詰めたグラスを 2 つ持ってきて、そこに注いだ。グラスの 4 分の 1
くらいまでが、琥珀色に染まる。同じ袋から炭酸水を取り出すと、それで薄めていく。パチパチと炭酸の音が弾けた。アルコールの香りが鼻を刺激する。それが私の前に差し出され、手に持つと勝手に乾杯される。グラスに口をつけるまでに、期待と未知への恐怖が入り混じった感情が紡がれる。彼が豪快に喉を鳴らす姿を見て、少し、警戒心が解けた。口にすると、喉を焼きながら胃まで落ちていくような感覚が襲ってきた。
「よく…こんなもの飲めるな」
苦虫を噛み潰したような顔で言う。
「口に合わなかったか?」
「そういう訳じゃないが…初めてだ。酒自体」
「マジかよ…言ってくれりゃあ良かったのに。他のに変えるか?」席を立とうとする彼を手で静止する。
「いや、いい。飲む」
ここでやめたらナメられそうという変なプライドから、意地を張ってしまった。そうか?と再び料理を食べ始める彼につられて、私も同じように食べ始める。
「ごちそうさまでした」
どんぶりが空になる頃には、グラスも同じようになっていた。
「来た甲斐があったな。お前が旨そうに食べてる姿見て満足したし、片付けしたらお暇するわ」
「その…、ありがとう…」
「いいってことよ」
嬉しそうに笑う横顔が、少し紅く染まっていた。酒のせいかもしれないが。
私も食器を片付けようと席を立つと、目眩でバランスを取り損なってしまう。頭を押さえながら壁に手をつくと、アイザックが心配そうにキッチンからすっ飛んで来た。
「おい…酒弱いんだな。まったく…」
ぼーっとしていると、レンジャーロールで軽々と肩に担がれ、寝室のベッドに静かに落とされる。傍に座る彼に、頭を撫でられる。
「もう寝とけ。おやす──」
彼の腕を力が入らない手で握りしめ、引っ張る。潤んだ視界では、彼の表情など見えなかったが、驚いた声の後に、彼の理性の糸が切れる音が聞こえた。
掴んではいけない糸だが、あの頃の私は、きっと、寂しかったんだ。ただそばにいてほしくて、引き止めた。酒の、せいだ。
◆
目が覚めると、乱れたベッドに私一人が沈んでいた。彼は、もう帰ったようだ。起き上がると、体が怠く、節々が、痛い。彼が作ってくれた夕食を食べ終えたあたりから、記憶に靄がかかったように思い出せない。だが、シーツの汚れから理解した。最低だ。彼も、私も。調子を狂わせる存在は、やはり苦手だ。反吐が出る。彼と私は男同士だ。それなのに、どうして。私を女のように思っているのか。トイレのドアを開け、便器まで続くタイル張りの床をふらふらと歩く。男に犯されたと思うと、鳥肌が立つ。便器に手をかけ屈み込む。胃液が喉を焼きながら嗚咽と共に流れ出していった。嫌な記憶も、簡単に水に流せたら良いのに。
これ以降、彼は、度々私を欲した。良くしてくれる彼に嫌われる度胸もなくて、されるがままに、そのままズルズルと関係が続いた。
◆◆
「もう終わりにしよう?」
やっと伝える事ができた、私のその言葉は、返事を得ることなく、私の身体と共に彼の腕の中へ包み込まれた。いや、否定の意なのか。私の唇にキスが落とされる。こういう時に限って、溶けるような優しさを向けないでくれ。恋人でもないのに。
「なんだ、好きな奴でもできたのか?」
「…そうだ」
もちろん嘘だ。流れでつい言ってしまった。
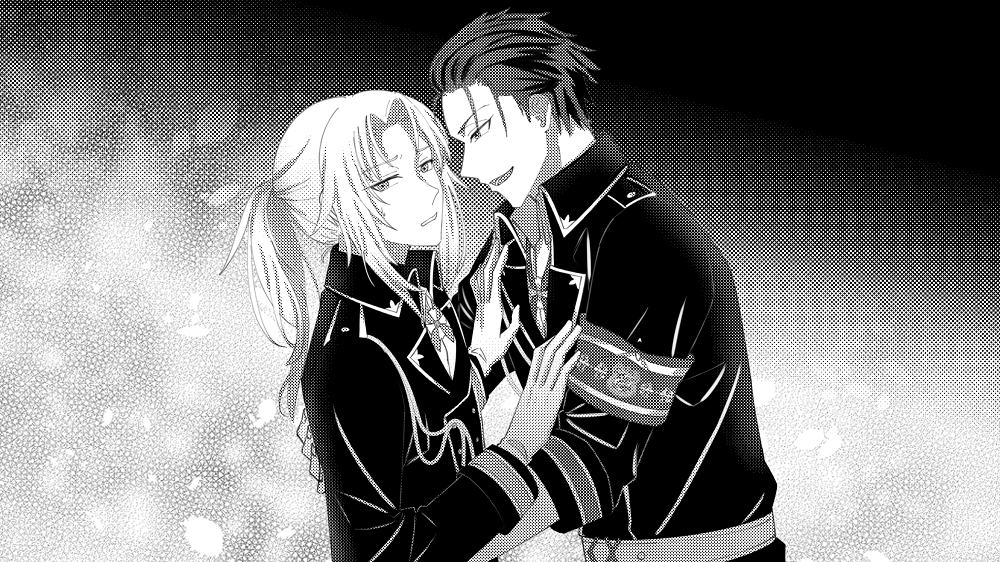
「っ…アイザック…!」
服の下に手を入れて敏感なところを触ってくる。私もそれなりに鍛えていて、一般よりは力があるくらいなのだが、やはり彼には叶わない。彼の前から、逃げ出せない。太陽のような、黄味がかった紅い瞳が、私を焦がす。その迫力に、思わず目を逸らす。
「嘘つけ。何で目逸らしたんだよ」
嘘がすぐに見抜かれてばつが悪い。何も返せなくなる。もう、嫌なんだ。欲望を処理するためだけの関係は。私以外でもそれはできるはずだ。都合がいいのが、腹が立つ。それでも、無視できないんだ。彼のせいで、いらない知識が増えていく。知りたくなかった。
「ほら、溜まってんじゃねえか」
「…っ…」
また、こうやって逃げられるんだ。彼の雰囲気に毎回絡め取られる。スイッチが入ってしまったら、もう聞く耳を持ってもらえないだろう。
「レイ…」
私の名前を呼ぶ彼の声が、皮肉のように、甘く、私の体に染み渡る。
「…っく…」
◆◆
戦争が激化し、交戦地域にある拠点の一つを、夜間に集中して制圧する作戦を実施することになった。この任務は、5、6、7、8 番隊が受け持ち、1、2、3、4 番隊は、その周りの拠点を死守する。
周りから攻められては一溜まりもないため、精鋭部隊を配置している。6〜8 番隊が到着するまでは5番隊がその拠点を守る。
長きに渡る交戦で物資が底を尽きようとしていたため、兵糧などの物資がありそうな拠点を攻めることを上に提案し、それが採用されたのだ。
私は、該当部隊からの報告を聞き、参謀部で審議し、その結果を下へ伝えていく任務を遂行していた。私が多くを担う任務を、今まで経験したことがなかったため、緊張で手汗が溢れる。緊張を抑えるために、コーヒーを飲んで、椅子に深く座りなおし、落ち着こうとする。
ノックの音に再び空気が張り詰める。6〜8 番隊の突撃準備が完了したという報告を受け、5 番隊を撤退させ、周囲の部隊と合流し守備を固める命令を出す。彼ら次第だが、これで問題なく事が進むはずだ。
時計の短い針が 4、5 周くらいした頃だろうか。5 番隊の撤退が完了した報告を受け、6〜8 番隊を拠点に突撃させるように伝える。これは参謀部で議論した結果だ。私は、現地で剣を振るうでもなく、ただデスクに座り、報告を聞いて戦況に合わせて指示を出すだけだ。出すだけだが、この役割を担う人間がいなければ、軍は成り立たない。
戦況が変化するのには、しばらく時間がかかるだろう。そう思って、参謀部の他の人に、少しの間交代を頼み、仮眠室で仮眠を取ることにした。だが、毛布に潜っても、頭が冴えて、眠りにつけない。何かあればすぐに言うように伝えたが…こういう時はアドレナリンが出て眠りにつけないのは当然だ。今回の作戦を遂行するに当たっての事前準備のせいで、ここ数日まともに眠れていないのに、不思議だ。もう何も考えまいと、薄暗い天井をただ見つめる。体温で温まってきた布団が心地良い。
「…て……さい!」
「起きてください!目的を達成しましたよ!ただ…」
鼓膜を大きく震わせる荒々しい声に、飛び起きる。どのくらい経っただろうか。いつの間にか眠っていたようだ。
「1 番隊の隊長と連絡が取れません」
「えっ…」
寝起きの頭に上手く情報が入っていかない。
「分かった。すぐに向かうから、きみには点呼と負傷者の確認をお願いしたい」
よく考えれば、1 番隊の隊長はアイザックが務めていた。彼は武力面ではとても優秀なのだが、よくふらっとどこかに行ってしまうのだ。困る。前にも似たようなことがあった。
「やはり、1 番隊隊長のみ連絡が取れません。それと、負傷者を数名確認したので、追加の医療班を現地に派遣しました。負傷者以外は順次帰還しています。」
参謀部の会議室に戻ると、私の代わりを務めてくれていた者から現状の報告を受ける。
「ありがとう。お疲れ様。」
他の雑事が忙しい中での作戦のため、こういう不測の事態では人手が足りない状況だ。
「すまないが、もう少し代わりを頼めるだろうか」
気づけば、彼がいる場所へ、馬を走らせていた。朝が来る前の空は、青と赤のグラデーションに染まっていた。道草癖を改めさせるために、彼に会ったらきつく叱る必要がある。
現地に到着し、設営された応急手当用のテントがふと目に止まる。嫌な予感から胸騒ぎがした。胸に巣食う霧を払うように、寝かせられている人の顔を順番に視界に入れる。そんな努力も虚しく、彼の顔はそこには見当たらなかった。どうして、こんなにも彼のことを考えてしまうのか。ここにいないとなると、戦場となった拠点付近にいる可能性がある。嫌な気分に突き動かされ、拠点を見て回る。
先程まで晴れていた空は、いつしかどんよりと重い雲に覆われていた。外壁が崩れかけたり火事になっていたり損傷が激しい。敵兵は撤退したのか、どこにも人の気配はなかった。単なる私の勘違いか。きっと、とっくに帰って、いびきをかいて寝ているのだろう。冷たく強い風と急に降り出した雨のせいもあって踵を返して戻ろうとすると、瓦礫の山の向こうから何者かが動く音が聞こえた。歩みを止めて音の方向を確かめる。耳をすますと、雨が当たる音以外に誰かが咳をしているのが耳に届く。そこに恐る恐る近づくと、私が踏んだ砂利の音で相手も気づいたのか、こちらを見てくる。
「よう……ごほッ…」
「…っ、アイザック…!!」
探していた人──アイザックが壁にもたれかかりながら座っていた。剣などの刃物による傷を多数負っていて、胸には矢が刺さっていた。肩で息をしながら苦しそうに咳をしている。その唇からは鮮やかな血が垂れ、喀血していた。私に無理に笑顔を向けているが、このままでは失血死するだろう。彼以外、すべてが灰色に感じた。
「今…、手当てするから…動くな…!」
「…ッく…、よせよ、…もうじき死ぬ」
動揺して震える息と手で必死に治療しようとする自分と、死の危機に面しているのに呑気な彼は、端から見たらその真逆な温度差のせいで滑稽に感じるだろう。出ている部分の矢を出来るだけ綺 麗に折って、自分が着ている上着でそれが動かないように固定する。次第に雨が強くなり、体に 当たる雨粒は重さと痛みを増していた。かすかに聞こえていた彼の呼吸音がかき消される。切創 は傷が深く、圧迫しても、腐った果実を鷲掴みにしているように、紅い液体が止めどなく溢れる。
雨と血で手がぬるぬると滑り、血生臭い匂いに虫唾が走る。それは、彼の影で雨宿りをしている 乾燥した大地に、雨水と混ざりながらじわじわと染み込んでいった。
「弟を…よろしくな」
「っ…」
これから死ぬような、フラグが立つことを言わないでほしい。彼のことは好きではない。むしろ嫌い寄りだが、目の前で死なれたら嫌でもずっと記憶に残り続ける。
「オマエが…苦しそうな顔、すんなよ……笑っててくれ…」
「もう、喋らなくていい!!」
私を気にしている場合ではないだろう。力無い微笑みは血で汚れていた。頭を撫でようとした震える大きな手は、糸が切れたようにそのまま地面へと落ちた。
「アイザック…?……アイザック…っ!」
血塗れの手で彼の手を拾い上げ、強く握りしめる。いつもの彼なら熱いほどの温もりを感じるのに、今は氷のように冷え切っている。揺さぶりながら、その名を何回呼んでも、返ってくる返事はなかった。今になって、自分の濡れた体が冷えて寒く感じる。目の前で散る命は、どうしてこんなにも儚いんだ。色のない水が、暗い雲から私たちを打ち付ける。それからは、彼の閉じた瞼と血の気のない頰をゆっくりとなぞって落ちていく雫を、ただ、見つめていた。
後の報告と記録によれば、5 番隊が苦戦していることを知ったアイザックが、たった一人で援護しに行ったそうだ。持ち場が手薄になるのを心配して、1 番隊隊員までは連れて行けなかったのだろう。5 番隊は負傷者が多かったものの、重傷者は少なかった。腕に自信がある彼のことだから、その場の全員を撤退させて自分だけが残って戦ったのだ。それは私が考えるべきことだったのに。命令が聞けなかったのか。お人好しにもほどがある。
◆◆
鬱陶しいのがいなくなって清々した──なんて、最初は思っていた。だが、太陽と月が交代を繰り返すうちにそんな感情は隅へと追いやられ、寂しさと悲しみに変わっていた。私があんな作戦を提案しなければ、医療の技術があれば、彼はまだ私の隣にいたかもしれないのに。私のせいだ。もう一度、あの不健康そうな肉まみれの料理が食べたかった。彼がいなくなってから、私を取り巻く空気はまるで太陽が消えたかのように冷え切っていた。今でも、彼を探してずっと彷徨う夢をよく見る。あの時流れなかった涙が、今更、私の顔をぐちゃぐちゃにする。本当に、馬鹿だ。彼を忘れられないんだから。ふとした瞬間に思い出してしまう。目の前で死んでいく人を助けられなかった後悔と彼がいないことによる寂しさが心を掻き毟る。だいぶ落ち着いてきた今だからこそ冷静に自分の感情を整理し認識できる。私はこれからずっと死ぬまでこの後悔という名の十字架を背負っていくのだ。
もし、今の私が、彼の死に際にタイムスリップすることができたとしたら、技術的に救うことは可能だろう。あの時の私には今ほどの医療知識はなかった。だが、そんな力を持ってしても、医者の使命を抜きにして私情で語れば、おそらく彼のことは助けないだろう。紅い太陽のような花は枯れてもなお、ドライフラワーのように私の心に存在している。これ以上彼の隣にいたら、私が私でなくなるような気がするのだ。もう囚われるのは終わりにしたい。どんなにもがこうと、彼とのあの日々はもう二度と取り戻せないことは頭では分かっているのだ。それに、今の私には
守りたい人がいる。
墓に花を供えた後に、彼が亡くなった場所を訪れる。
廃墟同然の廃れた拠点には、何事もなかったかのように草花が生い茂っていた。寒さに強いものが地面を埋め尽くす中、暖かくなる頃に咲くであろう花が一際目立って風に揺れていた。時期尚早なそれ──黒いチューリップが一本だけ、静かに咲いていた。
視界が水浸しになり、悲しみが頰を伝う。私の心境とは裏腹に、空は遠くまで透き通るように、晴れ渡っていた。こんなので、私を励ましているつもりか。
最初から最期まで、最低だ。
冬にしては暖かい風が、私の髪を滅茶苦茶に撫でて、去っていった。
