Secret Novel
Secret
Novel
シークレット小説
大切な相手
夜明けが近づき空が白み始めた頃。
ベッドからはみ出た体温のない右脚に口付けながら、ダンは訊いた。
「この脚…どうしてこうなったん?」
こちらを見ていない彼には、口付けたところで感触も体温も伝わらない。そう判っていて、何度も口を、舌を這わせる。あまりキスをしたがらない彼に気づかれていないことをいいことに、好きなだけ想いを乗せることのできる右脚への口付けが、ダンは好きだった。
今まで気になってはいたが、ずっと聞けなかった疑問。けれど、『こんな関係』になってもう1年以上経つ。今晩──もはや昨晩なのだが──のバイオレットの態度を見ても、自分だったらもう、尋ねてもいいような気がした。
「昔、大切な相手を亡くしてね。その時に」
不快感を露にされるほどではないだろうと思ってはいたが、想定以上にあっさりと、しかも重たい回答が返ってきて、むしろこっちが戸惑う。
「ふぅん…」
今、それ以上深く聞いていいのか分からず、曖昧な返事になった。
先程まであった甘さの残る空気が消えてゆくのを感じる。
「君を見てると、たまに彼を思い出すよ」
「え?」
「喜んでる時とかのリアクションがなんか…少し…似ている」
それは一体、どういう意味で言っているのだろう。"大切な人"との記憶が、思い出しても辛いものではないということか、それとも。
自分が大切な人に重ねられているという事実に、若干の嬉しさと切なさと嫉妬が入り混じり、複雑な感情を形成する。
「つらい?」
「いや」
「ほんならええわ」
少なくとも、ダンを見て思い出すことで辛くなることはないようだ。それなら、問題ない。
たとえこの関係が”彼”と重ねることで生まれたのだとしても、それなら”彼”を思い出せないほどに自分を植え付ければいいだけだ。
「…なあ、もっかい、ええか?」
「……もう朝になるよ」
「明日はなんも用事あらへん言うてたやろ」
「……しょうがないな、君は」
こうして許してくれることに、卑怯だと思っても、甘えるのだ。
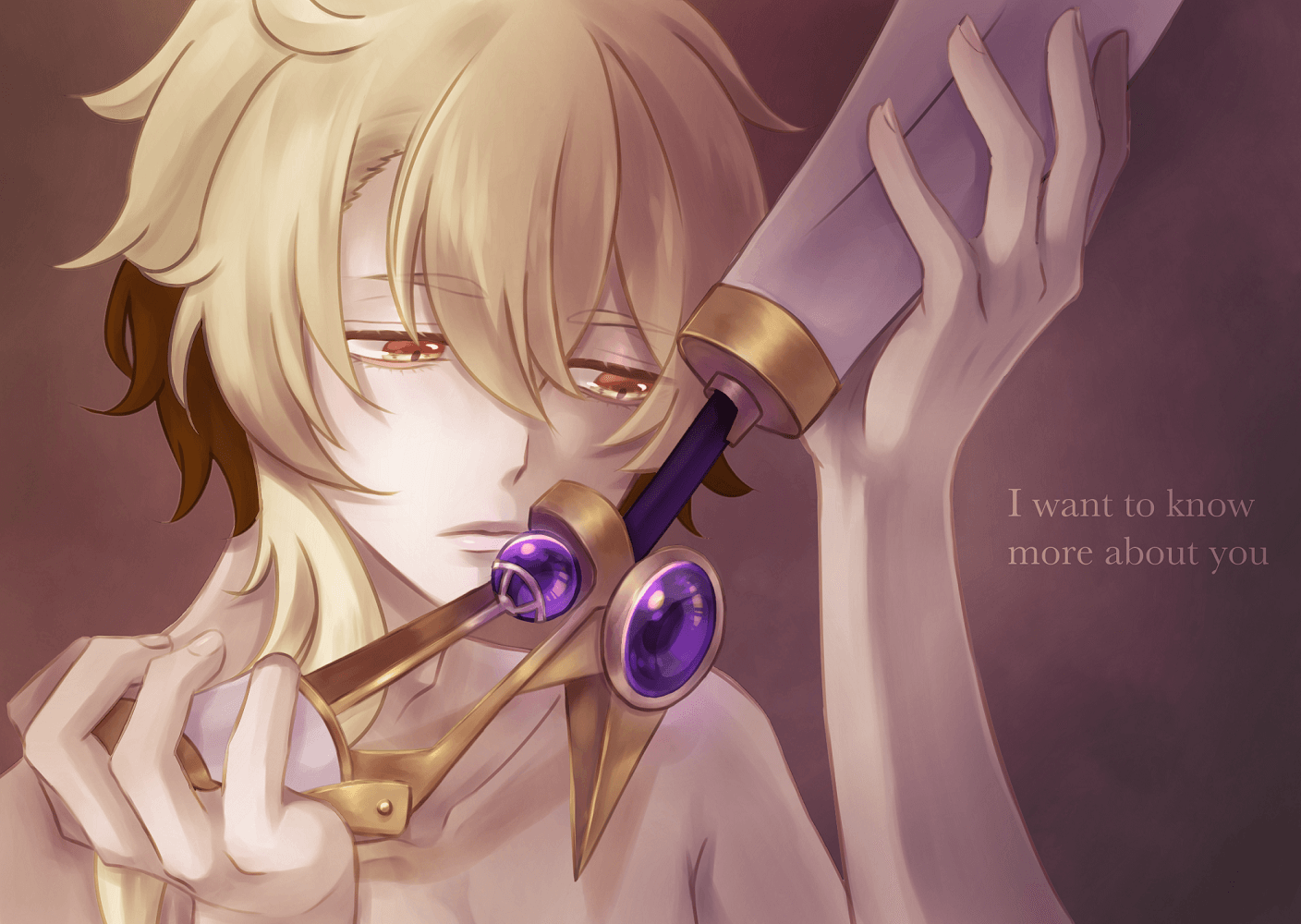 ◆◆◆
◆◆◆
「大切な奴って、どないな奴やったん?」
いつものバーのカウンター。マスターは向こう側の客と話している。周りに客もおらず、ダンはあの日からずっと気になっていたことを尋ねた。
「どんな……。そうだね、僕と一緒に働くのをすごく喜んでくれて、誰からも好かれていたよ。人と打ち解けるのが早くて…頭もよかった。とても頼りにしていたよ」
「へえ。…ええ奴やったんやな」
「ああ、本当に」
聞かなければよかった。
嫉妬と苦しさで胸が捩れそうになる。
聞いてしまってはもう遅い後悔。
一緒に働くのが好き?人と仲良くなりやすい?なるほど、そら、俺にも似てるわな。ま、俺とちごうて頭はよかったみたいやけど。
そんな完璧な人間に、自分が勝てるとでも思ったのか。自分の体の一部を失ってまで、助けようと思った相手に?
自分の傲慢さに、笑いすら込み上げる。
死んだ人間はもう戻らない。勝負することすら叶わない。思い出は美化され、時間が経つほどに高尚なものへとなってゆく。
これが、辛い思い出ならまだよかった。そんな記憶忘れさせてやるって、つけ込む余地があったのに。
先日思ったこととは正反対の感情。
だって、勝ち目ないやんかそんなん。
頭良くて、頼りになる?
俺はみんなに不思議ちゃん扱いされて、頼りになるどころかいっつも迷惑かけて、頼ってばっかや。きっと今俺がピンチになっても、命張ってまで助けようとまでは思われへん。
そんなん、無理やん。
「いつも私の仕事を手伝ってくれてね…ただちょっと甘えん坊でね、大事な作業中でもじゃれてこようとして、でも邪魔しちゃいけないから、少し離れたところでじっとこっちを見てくるんだ。そんなところがいじらしくて。…僕はつい作業の手を止めて、構ってしまう。ちょっと困ったよ」
全然困っていないような嬉しそうな顔。そんな顔、初めて見た。
思っていたより、何倍も、仲がいい。仲がいいどころか、それ以上に。
だめだ、嫉妬で狂いそうになる。
「普段は穏やかなんだけど、庭で遊んでる時は結構活発で、何度も押し倒された」
くそ、聞きたくない、聞きたくない。そんなの、「信頼できる親友」どころじゃない。恋人じゃないか。
大切な人、という言葉に覚悟はしていた。けれど、恋人だと決まったわけじゃないと、悪あがきをしてその可能性は考えないようにしていた。
けど、もう、聞いてしまった。誤魔化しようがない。
「特に水遊びが大好きでね……。ホースを持って水を出してやると、千切れるほどに尻尾を振って飛びついてきた。懐かしいな」
…?
ちょっと待て。
……尻尾?
「はは、ちょっと喋りすぎちゃったかな」
「あのぉ…ちぃと聞きたいんやけど」
「何?」
「そいつって…ペット?」
「? そうだよ。…愛犬のゴールデンレトリバー」
は。
は、はは。
「大切な人て、犬なん!?」
「そう。大切な『犬』だよ」
思い出してみれば確かに、「大切な相手」とは言っていたが、「大切な人」とは言っていなかった。……気がする。
「ちょお待ってや。なんやそれ…」
じゃあ一体、自分は何に嫉妬して、何に苦しんでいたのか。
思わず顔に血が上る。
「どうしたの、ダン。顔赤いよ。酔った?」
「いや…」
先程までの言葉も、捉え方が変わってくる。
なんや、ちくしょう。自分はペットなんかに。…いや。
「『なんか』とちゃうわな」
「え?」
「そいつ。大切な相手やったもんな」
「ああ。そうだよ」
「この脚を失ってもいいと思えるほどに?」
「そう」
そうだ、たかがペットなんかじゃない。大切な相手なのだ。
でも単純な自分は、相手が人間じゃなかったことに安心してしまうし、それなら自分の入る隙もあるんじゃないか、なんて、思ってしまう。
「でも結局、助からんかった」
「……そうだね」
「俺は、そいつの代わりか?」
「まさか。誰だって、誰かの代わりにはなれないよ」
彼の菫色の瞳は、薄暗いこの店の中でも透き通るようだった。
「俺なら、アンタを残して死んだりなんかしない。こんな怪我も負わせない。だから、……そいつの代わりとは言わへん、この脚の代わりくらいにはさせてもらえへんか?」
「……何を言うかと思ったら」
バイオレットはいつもの仕方ないな、という表情でグラスに口をつける。
この表情が、好きだ。自分を受け入れてくれているという安心感。
「君は大きいし強いし丈夫だもんね。でも、大丈夫。僕は一人で立って歩ける。だから脚の代わりなんていらない。この義足もあるしね」
「……せやろな」
その返答は、なんとなく予想していた。
「でも、ずっと一人で歩いてたら、たまに疲れてしまうかもしれない」
「……」
「その時に、少し寄りかからせてくれると……嬉しい」
バイオレットは向こうを向いて、表情を見せてくれない。でも、酒のせいではないであろう赤く染まった耳だけで、十分だった。
「そんなん…そんなんいつでも! 俺はデカいから全体重かけたってビクともせんで!」
「ふふ。それは頼もしいな」
若干の赤みを残してこちらを見やったその表情は、”大切な相手”を語っているときと同じくらい、嬉しそうで、でも少し困ったようなものだった。
俺の大好きな、「しょうがないなあ」という顔。
俺を受け入れてくれるって、言葉よりなにより一番わかる顔。
もう少し自信持ってもええんちゃう? と、己の心に尋ねてみた。
心臓からの応えはない。でも、答えは目の前の彼が知っている。
